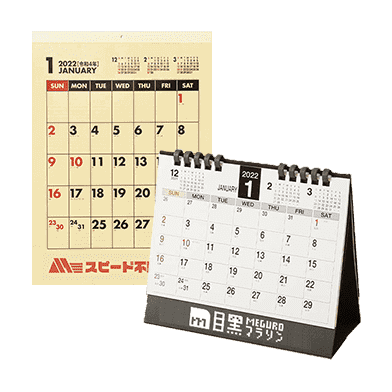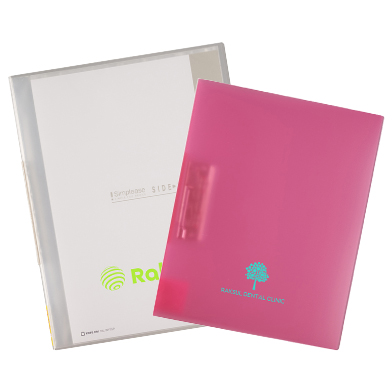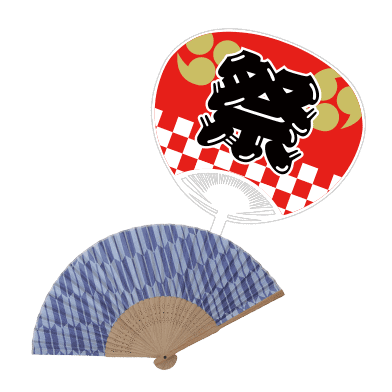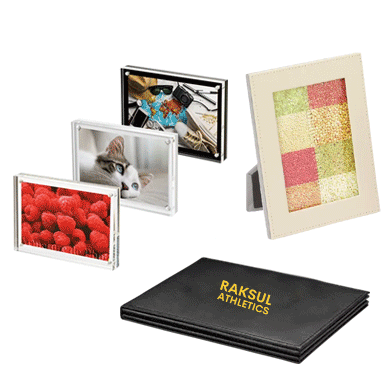記念品の勘定科目とは?
記念品を注文した場合の勘定科目とは?
会社の創立祝いや退職祝い、結婚祝いなどで記念品を作り、取引先や従業員に贈ることがあるでしょう。記念品を注文する際は、計上に適した勘定科目のチェックが大切です。 家族や友人などに贈るプライベートな記念品は経費として計上できません。一方で、取引先や自社の従業員などに贈る仕事関係の記念品は経費にできます。
従業員に渡す記念品は「給与」
自社の従業員に贈る記念品の勘定科目は原則的に「給与」として取り扱います。
そのため「給与課税」が行われて「源泉所得税」が発生します。
得意先など社外の場合は「交際費」
得意先に贈る記念品は「交際費」として計上できます。そのため自社の従業員とは異なり、税務処理上で課税する必要はありません。
従業員の記念品が「福利厚生費」と認められる場合
創業記念や永年勤続の記念品は、国税庁が定めるそれぞれの要件を満たせば給与ではなく「福利厚生費」として計上することができます。
記念品が福利厚生費になる要件
国税庁が定める一定の要件をすべて満たした場合、「給与」ではなく「福利厚生費」として計上できます。要件は、創業記念などの記念品と永年勤続者に支給する記念品や招待費用でそれぞれ異なります。
(1)創業記念などの記念品
①支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
②記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
③創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
(2)永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用
①その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
②勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
③同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
(引用:国税庁)
福利厚生費が課税対象になる判断基準
福利厚生費として損金を処理できるかどうかは、税務上の基準と照らし合わせて判断されます。税務上の判断基準とは、「機会の平等性」「社会通念性」「実費の精算」をいいます。
機会の平等性
福利厚生費として計上したい経費が全ての従業員が等しく対象になっている場合は、「機会の平等性」を満たしているといえます。限られた役員や従業員が対象になっている場合は一部の人だけに支給されることになるため、課税対象となります。
社会通念性
従業員の記念品にかかる費用や内容が一般的な常識や見解の範囲内であれば、福利厚生費として認められ課税対象外となります。記念品が高価すぎるものである場合は、課税対象となる可能性があります。
実費の精算
「実費の精算」とは企業と従業員の雇用関係に基づいて発生する業務に必要な費用のことをいいます。従業員が出張時に支払いを行って後日領収書を以て会社に精算する場合は、福利厚生費として計上することができます。従業員への記念品の場合は、旅行や観劇などへの招待費用は実費の精算にあたります。旅行券の場合は、支給後1年以内に利用することや支給額相当の旅行範囲であること、旅行券を使って旅行をしたという証拠を提示することが満たせば給与課税対象外になります。
税務処理上で記念品を選ぶときの注意点
税務処理上で記念品を選ぶときには、課税対象にならないと判断すると同時に注意すると良い点が3つあります。給与として計上しないリスクの認識と記念品を渡す対象、給与課税の対象になる記念品の種類を確認しておきましょう。
給与として計上しないリスク
課税対象として計上すべき記念品を給与として計上しなかった場合、記念品を受け取った従業員と会社双方にリスクがあります。まず、従業員に対しては所得税や住民税が徴収されます。記念品は基本的に会社から従業員に対して贈るものなので、あまり気持ちの良いものではありません。また、会社側では、国税庁から源泉所得税の納付漏れを疑われる可能性があり社会的な信用を失う恐れがあります。
特定の従業員に記念品を渡す場合
特定の従業員に対して記念品を渡す場合は、給与課税の対象になるので注意が必要です。全ての従業員が記念品を渡す対象になっている場合は「福利厚生費」として計上できますが、特定の役員や役職、部署に対して記念品を渡す場合は給与課税の対象になります。永年勤続表彰の記念品は、2回以上の表彰の場合は前回から5年以上の間隔を空けるなどの要件を満たす必要があります。
引用:国税庁「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」
給与課税の対象になるものがある
税務処理上で非課税となる記念品を選ぶ際は、給与課税の対象となるものを避ける必要があります。具体的には現金や商品券、プリペイドカード、受け取った人が自由に記念品を選べるカタログギフトなどの金銭を渡したものと同等の記念品は、金額を問わず課税対象になります。