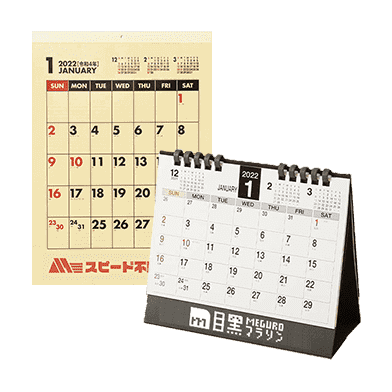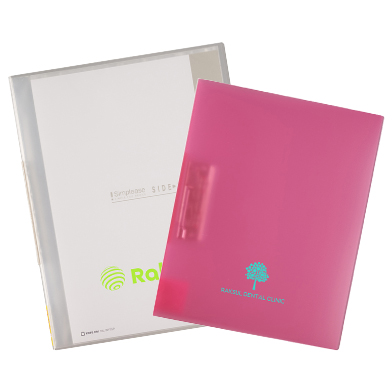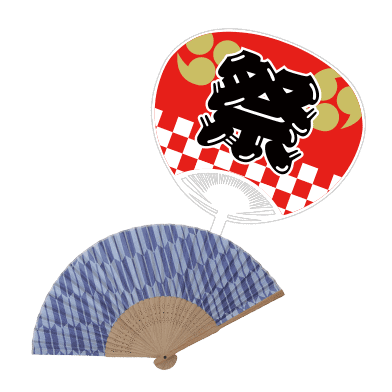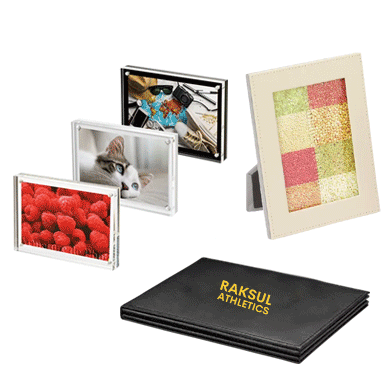景品表示法の上限金額とは?超えそうな場合の対処法
景品を消費者に配布する際は景品表示法を守る必要があります。上限金額は懸賞の種類によって異なるため、一般懸賞、共同懸賞、総付景品それぞれの定義と最高金額を把握しておきましょう。景品の上限金額を超えそうなときの対処法もご紹介します。
景品表示法とは
景品表示法の正式名称は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)。商品提供側が実物より商品を良く誤認させたり、過大な景品を付けたりすると、消費者が質の悪い商品を買ってしまうなどの不利益を被ることがあります。景品表示法は景品の表示や広告表現方法、最高額を規制することで、消費者の合理的な商品選択を確保する法律です。過大な景品によって事業者同士の景品競争がエスカレートしたり、誇大広告や高額すぎる景品によって消費者が不利益を被ったりすることを防ぐ役割があります。
「景品」の定義について
一般的に言われている景品はオマケや粗品、賞品などですが、景品表示法における景品は、 (1) 消費者を誘引する手段として (2) 取引に付随して提供する (3) 物品や金銭などの経済上の利益 を指します。 さらに景品は「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3種に分類され、それぞれ景品として提供できる商品の上限金額が異なります。
一般懸賞における景品の上限金額
消費者に対して、くじや抽選などの偶然生、特定行為の優劣などによって景品を贈ることを「懸賞」と言います。例えば、じゃんけんや抽選券などで景品を提供したり、クイズや競技の優劣などに応じて景品を提供したりすることも懸賞です。その中でも共同懸賞以外のものが「一般懸賞」と呼ばれています。
| 懸賞による取引価額 | 最高額 | 総額 |
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
共同懸賞における景品の上限金額
市町村の小売業者が共同で実施したり、「電気まつり」などで地域の同業者が共同で実施したりする場合は、複数の事業者が行う懸賞として「共同懸賞」になります。共同懸賞の景品類の上限金額は一般懸賞よりも高く設定されています。
| 最高額 | 総額 |
| 取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
総付景品における景品の上限金額
消費者に対して、懸賞ではない形で提供される景品は「総付景品」や「ベタ付け景品」と呼ばれます。商品の購入者や来店者にもれなく贈られる景品が典型例です。サービス購入の申し込み順などによって提供される金品もこちらに該当します。
| 取引価額 | 景品類の最高額 |
| 1,000円未満 | 200円 |
| 1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
景品表示法の金額を超えてしまいそうなときは
景品表示法に違反するとペナルティが科される場合があります。例えば限度額を大きく超える景品等を消費者に提供してしまった場合は、消費者庁から改善のための指導が行われ、景品提供を制限または禁止される可能性があります。従わなければ罰則が適用される場合もあるため、景品を提供する際は景品表示法の内容を確認し、「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」のどれに分類されるのか、またそれぞれについて上限金額はいくらなのかを確認しましょう。 景品が景品表示法の上限額を超えてしまう可能性があるなら、景品の見直しが必要です。まずは上限金額を確認してから適切な景品を設定してください。